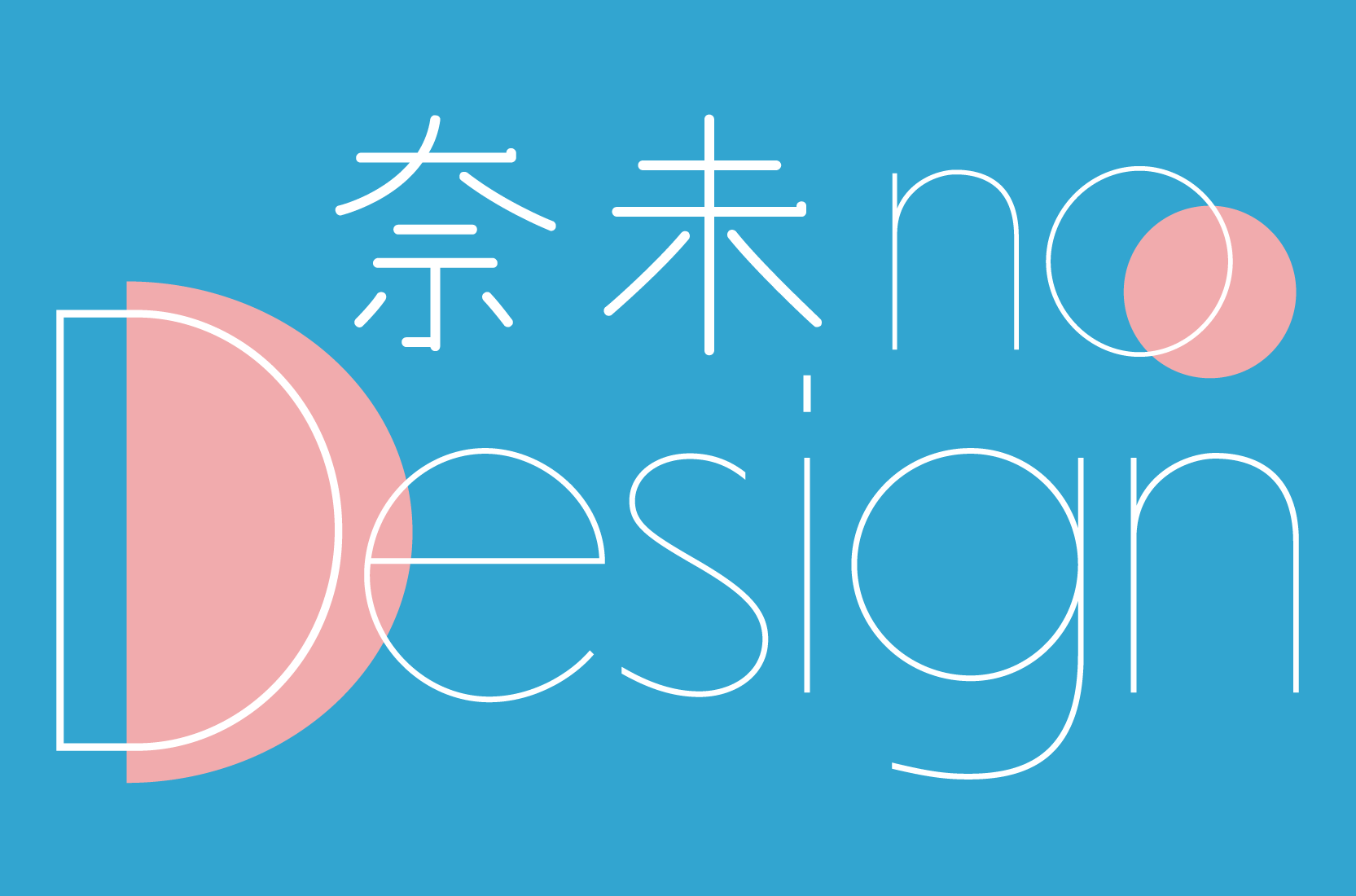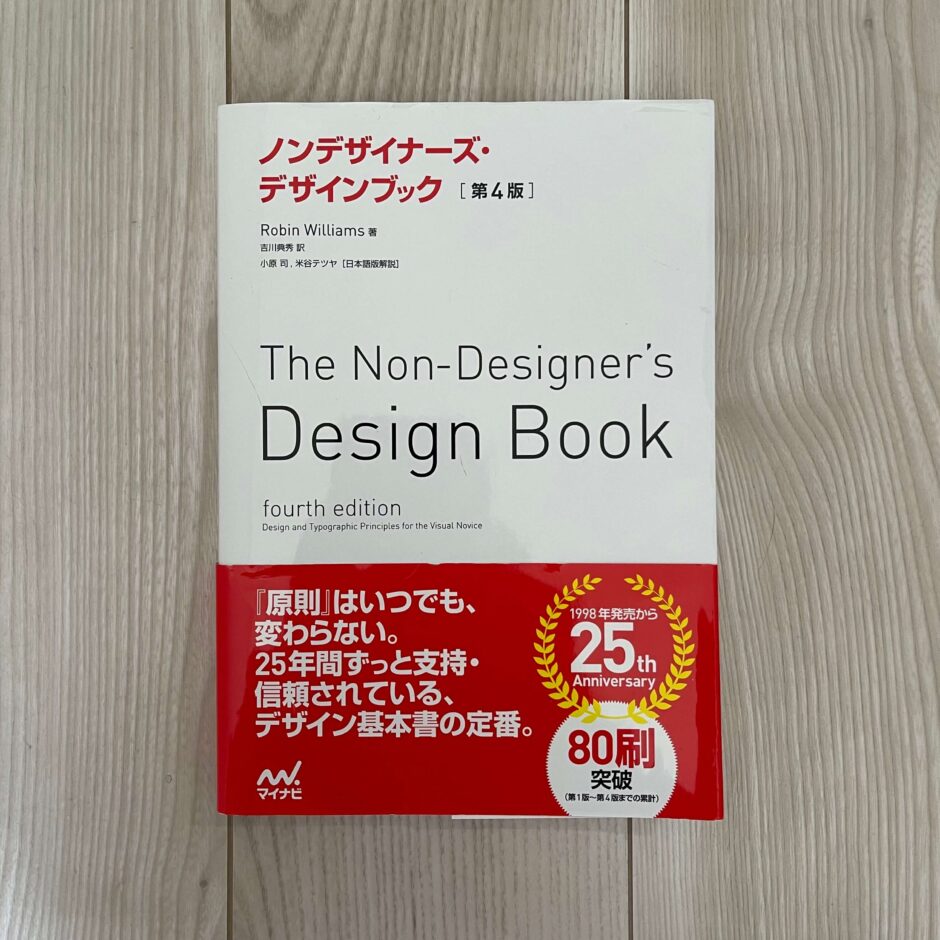【近接】
関連する項目をまとめてグループ化
同じような要素のものは近づけて配置する
近接は関係があることを意味する
近接化により空白も作り出すことができる
視線の流れを意識する
どこから見始めるか、どういう道筋をたどるか、どこで見終わるか、読み終わった後どこに目がいくか
【整列】
ページ上すべてのものを意識的に配置する
一体性はデザインにおける重要なコンセプト
力強い線を存在させる
整列が強力ならそれを意識的に崩すことができる
崩すなら大胆にやる
中央ぞろえにする癖をやめる
中央ぞろえにするなら「とりあえず」ではなく意識的に
【反復】
デザイン上のある特徴を作品全体をとおして繰り返す
孤立している部分が結び付き、作品が一体化され強化される
反復させている要素をさらに強化させる(アクセントをつける)
ただ反復させすぎには注意⚠️
【コントラスト】
コントラストは読者の目をページに引き込める
臆病になるとコントラストではなく衝突が生まれる
はっきりと異ならせること
情報の組み立てが読者に一瞬で分かるようにするべき
チップス
【名刺】
・絶対に必要な情報以外は取り除く(全ての情報を入れようとしない)
・フォントは大きすぎると野暮ったく見える(10ポイント以上)
名刺にはお客様がほんの1,2秒で見る必要のある情報が入ってる
フォントを大きくすることより、名刺の全体的なデザインの方が年配の方も読みやすい可能性もある
【チラシ】
見る人の目を惹きつけるために、ちょっと変わったフォントを使う絶好の機会
絵や写真を予定した大きさより2倍にしてみる
見出しも24ポイントではなく400ポイントにしてみる
ページ中央に14ポイントの文字1行、ページの下に小さな文字ブロックというミニマリスト的なチラシも作ってみる
人は普通じゃないものなら立ち止まって見ようとする
チラシでは本文を小さいフォントにしても大丈夫
最初に読者の注意を引いてしまえば小さくても読んでくれる
強い焦点とコントラストを使って情報を組織化し、読者の視線をページ全体に導く
※全ての要素を大きくすると読者の注意は引けない
どこでそのチラシが見られるかということは、どうそれをデザインするかに非常に関係する
郵便チラシ→多くの情報を入れられる
売店のチラシ→主な特徴が一目で簡単に読み取れるようにする
日本語では縦読みもできる
→ 横書きの場合は無意識に縦読みにならないように、少し広めの行間設定にすると読みやすくなる
アルファベットの行間が1の場合は1.2倍くらいにする
フォント
【下線】
下線は絶対に使わない
下線はもともとイタリック体で印刷したい箇所の版組をする植字工に指示するために、タイプライターで使う視覚的な目印だった
下線以外にも強調できる方法はたくさんある
【カーニング】
カーニング=文字の間の微細なスペースを取り除く処理
それぞれの文字形のせいで余分なスペースがあるから、それを目で見て調整していく
【ウィドーとオーファン】
ウィドー:段落の最終行に7文字以下しか存在しない最終行
単語一個はもちろんだが、ハイフネーションされた単語の後ろの部分だけ残った場合は最悪
オーファン:ページの最下行に小見出しのみ1行しか入らなかったり、パラグラフの最初の1行しかそのページに入らず、残りが次ページに送られてしまうこと
【段落のインデント】
正しい空きはemスペース1個(=使用する活フォントのポイントと同じサイズ)
例) 12ポイントのフォントを使えば段落のインデント幅は12ポイント
※インデント= 文章の最初の部分に空白を挿入して、文字列の開始位置をずらす機能
【リスト】
リストにはハイフン(-)ではなく
ビュレット(●)もしくは装飾フォントを使う
活字
ほとんどのデザイナーは1つのページで複数のフォントを組み合わせる場合、思いつきですませる傾向がある。
しかし、コントラストを認識すると今度はそれを支配できるようになる。そうなると、衝突している問題の原因をもっと早く見つけ、さらにおもしろい解決策を見つけることができる。
【協調】
スタイル、サイズ、太さなどのバリエーションがあまり多くなく、1種類のフォントだけを使った場合に生じる。
そうすることで、ページの調和を保ちやすく、落ち着いてフォーマルな印象を与えるが、時にはただ退屈な印象を与える。
(協調がダメなわけではなく、どのような印象を与えるかを認識しておく必要がある)
結婚式の招待状でよく見る
→ 意識的に協調にするべき(フォーマルだから)
【衝突】
スタイル、サイズ、太さなどが似ているフォントを組み合わせた時に生じる。類似性は混乱を招く。
(視覚的に同じでもなく全く違くもないから衝突する)
すごく似てるけど本当は違うフォントを2種類使うと、間違えてるように見えてしまう。だから似ているフォントを使うと衝突する。
線や図形なども同じ。違う太さだけど、微妙に違う太さだと衝突する。
衝突は避けるべき!
【コントラスト】
この世のすべての性質は、単にコントラストによって成立している。それ自体で存在するものは、何もない。
by Herman Melville
コントラストを作り出すことは楽しいし、目を引きつける。コントラストを生み出す最も効果的な方法は、活字を使うこと。
デザインにとって大切なのは情報を伝達すること。
違う種類のフォントを組み合わせるのは、情報伝達を強化するためで、混乱させるためではない。
活字でコントラストを付ける方法
・サイズ
・太さ
・構造
・フォーム
・方向
・色
フォントの組み合わせで何が悪いのかを見つけるのが難しい場合は、「違うところ」ではなく、「似ているところ」を探すようにする。類似性が問題を起こしている。
コントラストを付ける場合には「臆病にならないこと」
活字のカテゴリー
・オールドスタイル
・モダン
・スラブセリフ
・サンセリフ
・スクリプト
・デコラティブ
全部大文字は読みにくいしスペースが必要
どんな単語も長方形という同じフォームになる
→デザイン的な見栄えのために全部大文字はOK
ただ、読みにくくなるということを認識しておくこと
同一カテゴリーの書体を同一ページに置くのはNG
→ 必ず衝突を起こすため
2種類の書体を使う場合は異なるカテゴリーから選ぶこと → コントラストが生まれる
最初はセリフ体とサンセリフ体を選ぶといい
サンセリフ体はたくさんの種類があるから組み合わせるのOK
その場合は、コントラストを強調するべし!
ローマン体とイタリック体やスクリプト体の対比もいい!
ローマン体:文字まっすぐ
イタリック体・スクリプト体:文字が傾いたり、流れてる
文字を傾けるのはやめる
傾けるメリットをちゃんと伝えられる時のみ使う
右上がりに傾いてる文字:積極的なエネルギーを生み出す
右下がりに傾いてる文字:消極的なエネルギーを生み出す
真っ直ぐにページを横切っているだけでも方向がある
活字の行は水平の方向を持っている
細長い「段」は垂直の方向を持っている
横切る太い見出しと細長い段組みでできた本文とは面白い方向のコントラストを作り出す
赤やオレンジなどの暖色は前に出てきて私たちの注意を引きつける
青や緑などの寒色は私たちの目から遠ざかる
寒色は広い範囲に使っても大丈夫
効果的なコントラストを付けるためには思ったより多くの「寒色」が必要
タイポグラフィの世界ではページ上の白黒の活字も色をもつものとして扱う
色は、文字の太さ、構造、フォーム、文字内の空白、文字間、行間、活字のサイズ、xハイトのサイズなどのバリエーションから生まれる
声が、重要な言葉に強さを加えるように、活字も、サイズの違いで、叫んだりささやいたりする。
声が調子で、言葉におもしろみを加えるように、活字も太さの違いで、調子を変える。
声が抑場で言葉を色づけるように、活字も書体の選択で、優雅にも在重にも頑丈にもできる。
Jan V. White
細くて軽い書体を文字間と行間をあけてレイアウトすると、とても明るい色(テクスチャー)が生まれます
太いサンセリフ書体をぎっしり詰め込むと、暗い色が生まれます
これは図版のない文字だらけのページで特に役立つコントラストの付け方です
灰色の文字だけのページは見た目に退屈で読む気も誘いません
見出しや小見出しに太い文字で色をつけたり、引用文や短い挿話をはっきりと違う色で組んだりすれば、視線が引きつけられるので、読む可能性が高くなる
欧文の活字は文字ごとに固有の高さと幅をもっているが、和文の活字は同じサイズの正方形に収まるようになっている
漢字は文字間が詰まってるように見えるから、場合によってはカタカナやひらがなの文字間を詰める必要がある
ゴシック系書体:サンセリフ体にほぼ該当
可視性に優れており、見出しや小見出しに使われる
行書体・草書体:スクリプト書体に相当
明朝体:オールドスタイルによく似ている
可読性の点で優れており、長文の本文で使われる
①焦点を決める
読者に真っ先に見てもらいたいものを決める
②焦点を作る
強いコントラストを付けて焦点を作る
③情報を論理的なグループにまとめる
グループ間の関係を判断して、この関係をグループを互いに近づけたり話したりすることで表現
④整列の強化
活字や画像を配置する時は強い整列を作り出し、それを維持
⑤反復を作る
ボールド書体、罫線、ディングバッド、空間的な配置を反復に使う
協調的なデザインを作るつもりでない限り、読者の目を引くような強いコントラストを必ず付ける